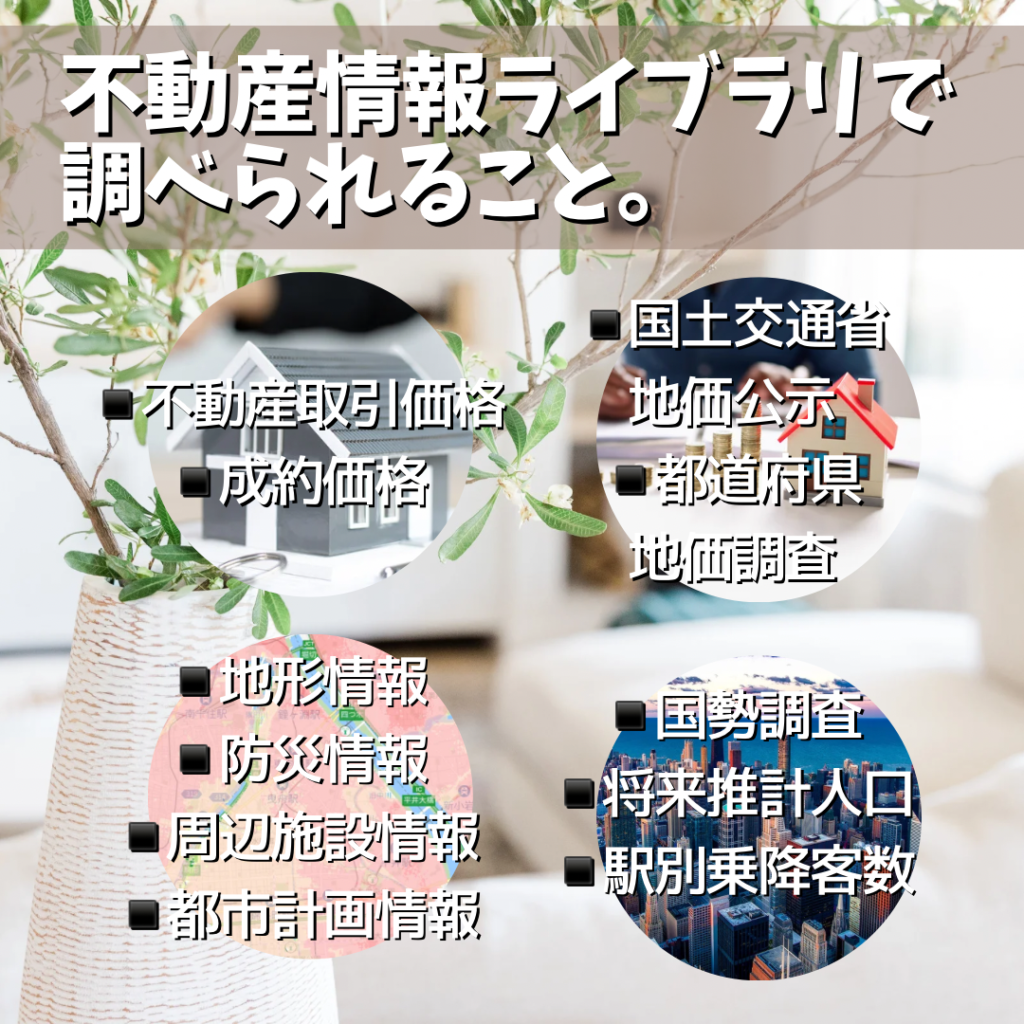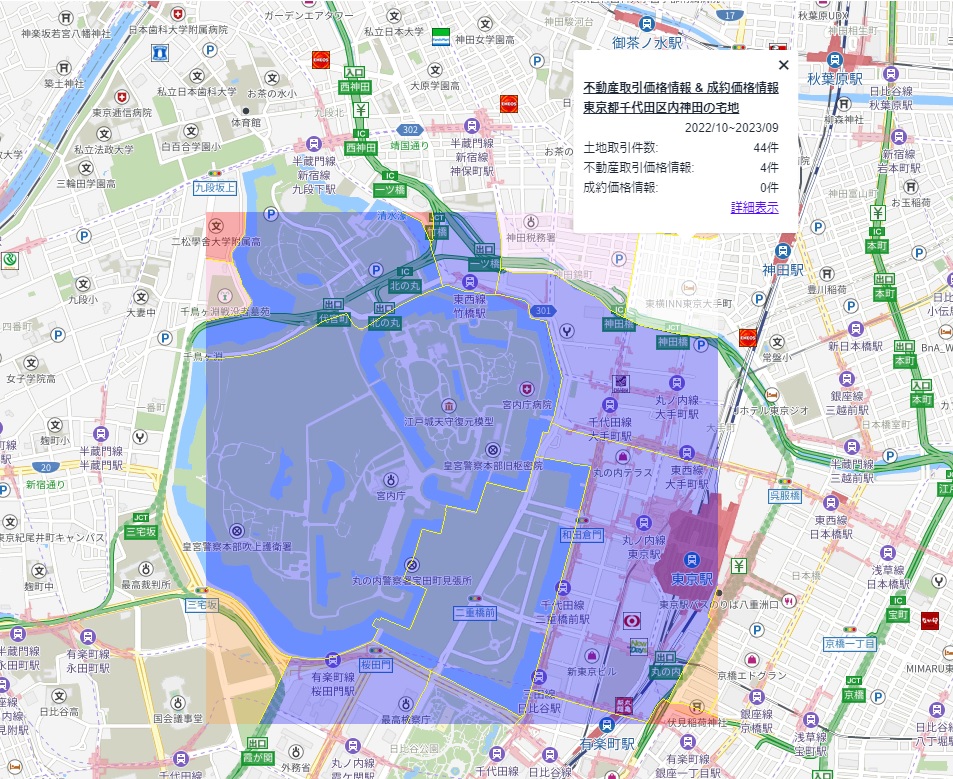2025年の東京23区の不動産市場は、「価格は高いまま、気持ちは慎重に」という空気が強まった一年でした。
新築マンションや新築戸建ては、建築費や人件費の上昇、用地不足を背景に、大きく値下がりすることなく高止まりを続けています。
「高いとは思うけれど、下がる気配もない」
そんな印象を持った方も多いのではないでしょうか。
一方で、中古マンションや中古戸建てについては、金利上昇の影響もあり、物件によって明暗が分かれ始めた一年でもありました。
立地や管理状態が良い物件は価格を保つ一方、条件によっては動きが鈍くなるケースも見られています。
2025年に感じた、住まい選びの変化

2025年を通して感じるのは、住まい選びの軸が確実に変わってきているということです。
以前は「家賃を払い続けるより買った方がいい」「今は金利が低いから、とりあえず買う」といった判断も少なくありませんでした。
しかし今は、「この家で、どんな暮らしができるのか」「この支払いを、無理なく続けられるのか」を立ち止まって考える方が増えています。
価格や市況だけで決めるのではなく、暮らしの実感を重視する姿勢が、2025年の大きな特徴だったといえるでしょう。
2026年展望|中古住宅は「育てる住まい」へ

2026年を見据えるうえで注目したいのが、中古住宅に対する考え方の変化です。
日本では長く、住宅は「年数が経てば価値が下がるもの」とされてきました。
建てては壊す、スクラップ&ビルドが当たり前だった背景には、税制や金融、住宅産業の仕組みがあります。
ただ近年は、国の住宅政策も「長く使う」「活かして住む」方向へ明確に転換しています。
長期優良住宅や住宅履歴情報の整備、脱炭素社会への流れもあり、良質な住宅ストックを活かす時代に入りつつあります。
東京23区で進む「中古住宅の再評価」

特に東京23区では、中古マンションを中心に変化が顕著です。
築年数が経っていても、立地が良く、管理状態が整っていれば、価格が大きく下がらない物件も珍しくありません。
また、「中古を買って、自分たちらしく整える」という選択も定着しつつあります。
中古住宅を完成品としてではなく、暮らしをつくるための器として選ぶ人が増えているのです。
2026年以降、価値が残る住まいの条件

今後、日本がすぐに「古いほど価値が上がる住宅市場」になるとは限りません。
ただし、2026年以降は価値が残る住まいと、そうでない住まいの差がよりはっきりしていくと考えられます。
評価されやすいのは、
・立地や生活利便性
・構造や管理の安心感
・修繕やメンテナンスの履歴
・間取りや性能を更新できる柔軟さ
そしてもう一つ大切なのが、暮らしを具体的にイメージできる空間かどうかです。
光の入り方や動線、余白のある間取り。インテリアの工夫次第で、住まいは何度でも心地よく生まれ変わります。
価格より、「続く暮らし」を基準に

2026年の東京23区の住まい選びは、「今、買えるか」ではなく、「この先も、安心して暮らせるか」がより重要になっていくでしょう。
新築か中古か、買うか待つか。正解は人それぞれです。
だからこそ、市況の数字だけに振り回されず、自分の暮らしと家計に合った選択をすることが大切です。
住まいは、日々の積み重ねの場所。
2026年は、価格だけでなく、「どんな毎日を送りたいか」から住まいを考える一年にしてみては いかがでしょうか。
LINE相談・個別相談のご案内
年末年始は、住まいについて考え直す方が増える時期です。
LINEでは、購入を前提としない、暮らしと家計を整理するご相談をお受けしています。
「まだ迷っている」
「何から考えればいいかわからない」
そんな段階でも大丈夫です。
2026年の暮らしを整える第一歩として、お気軽にご相談ください。